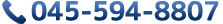遺留分侵害額請求の1年の期間制限について(「知った時」の意義)
2024/07/08
はじめに
遺留分侵害額請求に関しては、民法において、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」と規定されており、「知った時」から「1年」という非常に短い請求期間の制限があります。
本コラムでは、この点について、遺留分を害する遺言書の効力を争う場合における遺留分の請求期間について、最高裁昭和57年11月12日判決を参照しつつ、確認していきたいと思います。
よくあるご相談内容
遺留分や遺言に関するご相談を受けていると、ご相談者から「この遺言書は、被相続人(=亡くなった者)の意思に基づく遺言書とは到底考えられない」と相談されることがよくあります。ご相談者がそのように主張するケースでは、ほとんどの場合、発見された遺言書の内容が、相続人(多くは子)たる相談者の遺留分を侵害している内容となっています。
例えば、次のような例になります。
【例】
高齢の父が亡くなり、子2名(長男、二男)が相続人。
父の自筆の遺言書が発見され、「長男に全て相続させる」という内容であった。
二男は、これに納得がいかないため、遺留分侵害額請求というよりも、遺言が無効であると争いたい、と考えている。
上記のようなケースにおいて、相談を受けた当職(弁護士)としては、「遺言の有効性を争う場合でも、『万が一、遺言書が有効であったとしても、遺留分侵害額請求をする』という内容証明郵便は、必ず出しておいてくださいね」とアドバイスすることにしています(もちろん、ご依頼をいただけば、この内容証明郵便は、弁護士が作成し、通知します)。
この場合、遺言自体が無効なのだから、遺言の存在を前提とした遺留分請求をすることには心理的に抵抗がある、とおっしゃる方が多くいます。
もちろん、遺言無効訴訟を提起して、その遺言が無効となれば、通常は、遺留分の問題にはならないため良いのですが、仮に、遺言無効訴訟で勝訴することができない場合(遺言が「有効」となった場合)には、上記のとおり予備的にでも遺留分侵害額請求行使の通知をしておかないと、後日、遺留分侵害額請求権が時効によって消滅したと判断される可能性があります。
昭和57年11月12月最高裁判決をふまえての解説
この点、「遺留分減殺請求」の時代の判例として、最高裁判所昭和57年11月12日判決があります。この判例は、遺留分を害する生前贈与が無効であることを争っていた相続人が、遺留分請求をしていなかったという事例になりますが、最高裁は、民法1048条(旧1042条)の「減殺すべき贈与があったことを知った時」(1年の時効の起算点)の解釈として、「遺留分権利者が、(生前贈与の)無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことが、もっともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当」と判断しています。
この最高裁判決は、生前贈与を前提にした判例ですが、遺留分を害する内容の遺言書が存在した場合にも同様の考え方ができるものと考えられます。
そして、判例がいう「無効を信じているため遺留分減殺請求権(※現:遺留分侵害額請求権)を行使しなかったことが、もっともと首肯しうる特段の事情」がどのようなケースで認められるのかは不明確ですから、遺留分を害する生前贈与があった場合はもちろんのこと、遺留分を害する遺言書が存在し、これを相続人が無効と考え争っている場合でも、念のために、遺言書の存在を知った時から1年以内には、遺留分侵害額請求の意思表示を行っておいた方がよいと考えます。
最後に
本コラムの遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点(「知った時」)の問題もそうですが、相続や遺留分の問題は、とても専門性が高い分野になり、どの弁護士に相談するか、どの弁護士に依頼するか、がとても重要になります。当事務所では、相続・遺留分の問題を数多く取り扱っていますので、相続・遺留分の問題でお困りの方は、是非、当事務所へご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
最高裁昭和57年11月12日判決(抜粋)
民法一〇四二条(※現:1048条)にいう「減殺すべき贈与があつたことを知つた時」とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時と解すべきであるから、遺留分権利者が贈与の無効を信じて訴訟上抗争しているような場合は、贈与の事実を知つただけで直ちに減殺できる贈与があつたことまでを知つていたものと断定することはできないというべきである(大審院昭和一二年(オ)第一七〇九号同一三年二月二六日判決・民集一七巻二七五頁参照)。しかしながら、民法が遺留分減殺請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば、遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりにすぎない場合であつても時効は進行を始めないとするのは相当でないから、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があつて、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもつともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知つていたものと推認するのが相当というべきである。