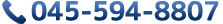特別の寄与料について(平成30年改正相続法シリーズ)
2020/02/11
平成30年相続法改正により、民法1050条が新設され、相続人以外の親族(特別寄与者)に対しての特別寄与料制度が制定されました。
本コラムでは、この特別寄与料について、解説します。
過去の裁判例で、相続人たる者の妻の特別な貢献を、その相続人の貢献と同視して、その「相続人」の寄与分を認めたものはありましたが、この例でもあくまで、直接的な経済的利益を受けるのは、相続人であって、実際に貢献をした妻本人ではありません。
しかし、現在の高齢化社会において、実際上、高齢者を引き取って面倒を見るのは、例えば、相続人たる長男の妻であるという例が多いため、「特別寄与料」制度は、このように、直接の相続人ではないものの「親族」であって、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした親族が、相続を契機に直接的な経済的利益を受けることができるように新設された制度です。
民法1050条1項は、特別寄与料について、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族…は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭…の支払を請求することができる」と規定していいます。
まず、「誰が」ですが、民法1050条1項は、請求者を「(相続人以外の)親族」に限定しています。
「親族」とは、民法725条において「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」をいうと規定されていますので、特別寄与料は、この範囲の者で、相続人ではない者が請求権者となります。
次に「誰に」対して請求できるか、ですが、これは、「相続人」に対して請求できるものと規定されています。
「相続人」が複数いる場合には、基本的には、その法定相続分割合で分割して請求します。なお、遺言によって相続分が指定されている場合には、その指定された相続分割合で請求していきます。
例えば、子3人が相続人の場合で、その内の長男の妻(1親等姻族)が特別寄与者であったとして、その特別寄与者は、子3人へ3分の1ずつ請求することができます(請求総額が300万円であった場合には、それぞれ100万円ずつ請求していく。ただし、この場合に、特別寄与者たる者は、自分の配偶者たる長男には請求しないケースも多いと思われる。この場合には、他の相続人へ100万円ずつ・計200万円を請求することとなる。)。
なお、法制定の過程で、事実婚(いわゆる内縁)の配偶者や同性パートナーを、特別寄与料の請求権者とすべきか議論があったようですが、この点は法制化はされておらず、特別寄与者は、あくまで「親族」に限られています。
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
本コラムでは、この特別寄与料について、解説します。
特別寄与料とは
これまで、被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した「相続人」に対する「寄与分」の制度(民法904条の2)はありましたが、この寄与分の制度は、あくまで「相続人」に対して具体的な相続分を増加させるという制度であって、相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、その相続を契機に、その特別な貢献をした親族に対して、経済的な利益を与えるという制度はありませんでした。過去の裁判例で、相続人たる者の妻の特別な貢献を、その相続人の貢献と同視して、その「相続人」の寄与分を認めたものはありましたが、この例でもあくまで、直接的な経済的利益を受けるのは、相続人であって、実際に貢献をした妻本人ではありません。
しかし、現在の高齢化社会において、実際上、高齢者を引き取って面倒を見るのは、例えば、相続人たる長男の妻であるという例が多いため、「特別寄与料」制度は、このように、直接の相続人ではないものの「親族」であって、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした親族が、相続を契機に直接的な経済的利益を受けることができるように新設された制度です。
民法1050条1項は、特別寄与料について、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族…は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭…の支払を請求することができる」と規定していいます。
誰が誰に請求できるのか
特別寄与料は、「誰が」「誰に」請求できるものでしょうか。まず、「誰が」ですが、民法1050条1項は、請求者を「(相続人以外の)親族」に限定しています。
「親族」とは、民法725条において「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」をいうと規定されていますので、特別寄与料は、この範囲の者で、相続人ではない者が請求権者となります。
次に「誰に」対して請求できるか、ですが、これは、「相続人」に対して請求できるものと規定されています。
「相続人」が複数いる場合には、基本的には、その法定相続分割合で分割して請求します。なお、遺言によって相続分が指定されている場合には、その指定された相続分割合で請求していきます。
例えば、子3人が相続人の場合で、その内の長男の妻(1親等姻族)が特別寄与者であったとして、その特別寄与者は、子3人へ3分の1ずつ請求することができます(請求総額が300万円であった場合には、それぞれ100万円ずつ請求していく。ただし、この場合に、特別寄与者たる者は、自分の配偶者たる長男には請求しないケースも多いと思われる。この場合には、他の相続人へ100万円ずつ・計200万円を請求することとなる。)。
なお、法制定の過程で、事実婚(いわゆる内縁)の配偶者や同性パートナーを、特別寄与料の請求権者とすべきか議論があったようですが、この点は法制化はされておらず、特別寄与者は、あくまで「親族」に限られています。
どのような行為をした場合に特別寄与料を請求できるのか
それでは、どのような行為をした場合に、この「特別寄与料」というものを請求できるのでしょうか。
民法1050条では、「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合を、特別寄与料の生じる場合としています。
やはり典型的なのは、相続人でない親族が、要介護状態にある高齢者と同居し、無償で療養看護をしたケースと考えられます。
条文上、「無償」性が要求されていますが、もちろんこれは、被相続人からびた一文もらってはいけないということではなく、当該療養看護の対価を既に受けていると評価されてしまう程度の経済的利益を受けていないという解釈になるものと考えられます。
民法1050条では、「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合を、特別寄与料の生じる場合としています。
やはり典型的なのは、相続人でない親族が、要介護状態にある高齢者と同居し、無償で療養看護をしたケースと考えられます。
条文上、「無償」性が要求されていますが、もちろんこれは、被相続人からびた一文もらってはいけないということではなく、当該療養看護の対価を既に受けていると評価されてしまう程度の経済的利益を受けていないという解釈になるものと考えられます。
いくら請求できるのか
それでは、実際に特別寄与料は、いくらとなるのでしょうか。
この点、まだ新しい制度ですので審判例の蓄積を待つ必要がありますが、一般的には、現行の寄与分の取り扱いが参考になるものと考えられています。
療養看護型の寄与分の代表的な考え方によれば、寄与分の額は、仮に第三者が療養看護を行った場合における日当額に療養看護の日数を乗じた上で、これに一定の裁量割合を乗じて算定するものとされています。
この点、まだ新しい制度ですので審判例の蓄積を待つ必要がありますが、一般的には、現行の寄与分の取り扱いが参考になるものと考えられています。
療養看護型の寄与分の代表的な考え方によれば、寄与分の額は、仮に第三者が療養看護を行った場合における日当額に療養看護の日数を乗じた上で、これに一定の裁量割合を乗じて算定するものとされています。
請求の期間と請求の方法
ここで、この「特別寄与料」の制度において、実務的にとても重要な点をあげます。
それは、請求の期間が、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したとき」までに限定されているということです。
しかも、この期間内に、相手方となる相続人に対して請求するだけではなく、家庭裁判所に対して、特別寄与料の調停を申立てる必要があります(特別の寄与に関する処分調停/裁判所のHPを参照ください)。
これは、実務的な視点からすると、極めて短期間のうちに、家庭裁判所へ調停を申立てなければならず、非常にタイトです。
実際上、弁護士へ依頼をして、この「特別の寄与に関する処分調停」を出すと想定した場合、弁護士も相談・依頼を受けてすぐに申立て準備ができるわけではありません。
戸籍謄本などの必要書類も集めないといけないわけですから、特別寄与料を請求したいとお考えの方は、相続人と協議するのは良いとして、それと並行してできる限り早期に弁護士へ依頼をすべきでしょう。
それは、請求の期間が、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したとき」までに限定されているということです。
しかも、この期間内に、相手方となる相続人に対して請求するだけではなく、家庭裁判所に対して、特別寄与料の調停を申立てる必要があります(特別の寄与に関する処分調停/裁判所のHPを参照ください)。
これは、実務的な視点からすると、極めて短期間のうちに、家庭裁判所へ調停を申立てなければならず、非常にタイトです。
実際上、弁護士へ依頼をして、この「特別の寄与に関する処分調停」を出すと想定した場合、弁護士も相談・依頼を受けてすぐに申立て準備ができるわけではありません。
戸籍謄本などの必要書類も集めないといけないわけですから、特別寄与料を請求したいとお考えの方は、相続人と協議するのは良いとして、それと並行してできる限り早期に弁護士へ依頼をすべきでしょう。
施行期日について
この「特別寄与料」の規定は、令和元年7月1日より後に発生した相続(死亡日が令和元年7月1日以降)に適用されます。なお、療養看護の行為が、同日より以前になされた場合でも同様に新法の規定が適用されます。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
民 法
(親族の範囲)
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
民 法
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。