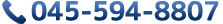療養看護型の「寄与分」(キヨブン)の実例
2019/11/18
相続において、亡くなった方(被相続人)の財産の維持又は増加に「特別の寄与」をした方がいる場合に、その方の「寄与分」(キヨブン)が認められるケースがあります。
寄与分が認められると、寄与分で認められた額が、その方の法定相続分にプラスされることになります。
この寄与分が認められるケースを類型化すると、
① 家業に特別に従事した場合(家業従事型)
(コラム「家業従事型の寄与分について」)
② 金銭等を亡くなった方へ出資した場合(金銭等出資型)
③ 亡くなった方の療養看護に特別に努めた場合(療養看護型)
④ 亡くなった方を長きにわたり特別に扶養した場合(扶養型)
などに分類されると言われています。
なお、いずれの類型も『特別』の寄与が必要ですので、親族間の通常の扶養義務を果たした程度では足りず、正に「特別に行った」と評価できる場合でなければなりません。
本ページでは、類型の中の「療養看護型」について解説したいと思います。
一般的に、療養看護型の寄与分の判断要素は、
(ⅰ)療養看護の必要性の強さ、
(ⅱ)特別の貢献といえるか、
(ⅲ)無償又は無償類似の療養看護か、
(ⅳ)継続期間、
(ⅴ)介護に専従したか(その程度)
などを考慮して「特別の寄与」といえるかを判断していきます。
ここで、実際に寄与分が争われた東京高裁平成29年9月22日決定のケースを見ていきましょう。
【事 例】
Xは、母Aと同居をし、平成22年から、Aが亡くなる平成26年まで自宅で介護した。
Aは、認知症を発症しており、要介護度は4(介護途中から要介護5)であった。
Aは、平日の朝夕30分、土日の朝夕60分のヘルパーによる訪問介護、週1回のデイサービス、月10回程度のショートステイ、2週間に一回の看護師による訪問看護、をそれぞれ利用していたが、それ以外はXが行い、食事の介助、摘便の処置、痰の吸引などを自分で行った。
Xは、仕事をしておらず、生活費として、Aから毎月10万円を得ていた。
【家庭裁判所の判断】
参考とする介護報酬を1日あたり要介護4の期間は6670円,要介護5の期間は7500円とし、ショートステイの日数は期間から控除し、デイサービス利用日の日数は、Xによる介護は半日として計算し、さらにここから割合を0.3減じて(※おそらく職業としての介護専門職による介護ではなく親族による介護であることを考慮したものと思われます)、約655万円をXの寄与分として認定。
さらに、痰の吸引処置をXが行っていたことについて約104万円を寄与分として認め、合計で約759万円をXの寄与分として認定しました(寄与分は法定相続分にプラスされます)。
【考 察】
この事例は、療養看護型の寄与分が認められたケースとして参考になります。
上記の判断要素から考察をします。
まず、(ⅰ)療養看護の必要性の強さ、については、Aは認知症で介護度も4ないし5ということですので、強い看護の必要性が認められます。
次に(ⅱ)特別の貢献といえるか、ですが、上記の介護度のAを施設に入所させずに自宅介護したことや、摘便の処置、痰の吸引処置を行ったことは、親族間の扶養義務の範囲を超える特別の貢献といえると認定されたものと考えられます。
(ⅲ)無償又は無償類似の療養看護か、についてですが、この点は、Xは、Aからの生活費(月10万円)で生活していたということなので、無償性については若干弱い部分があろうかと考えますが、それでも貢献度の強さから、療養看護の対価を受けていたとまでは評価されなかったものと考えられます。
(ⅳ)継続期間、については約4年の期間は、相当長期ですからこれが認められています。
そして、(ⅴ)介護の専従性については、基本的にAは仕事をせずに、自宅において療養看護に努めたようですので、これが認定できます。
以上のように、寄与分の認定は、なかなかハードルの高いものですが、超高齢化社会と言われる日本社会において、高齢の親を自宅に引き取り介護を熱心に続けるというご家族も増えていると思います。
そのような場合に、介護を全くしなかった他の相続人と同じ法定相続分では、むしろ不公平だと感じる場合も少なくないものと思います。
もし、寄与分を主張できるような相続問題がありましたら、是非一度ご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
参考
民法
寄与分が認められると、寄与分で認められた額が、その方の法定相続分にプラスされることになります。
この寄与分が認められるケースを類型化すると、
① 家業に特別に従事した場合(家業従事型)
(コラム「家業従事型の寄与分について」)
② 金銭等を亡くなった方へ出資した場合(金銭等出資型)
③ 亡くなった方の療養看護に特別に努めた場合(療養看護型)
④ 亡くなった方を長きにわたり特別に扶養した場合(扶養型)
などに分類されると言われています。
なお、いずれの類型も『特別』の寄与が必要ですので、親族間の通常の扶養義務を果たした程度では足りず、正に「特別に行った」と評価できる場合でなければなりません。
本ページでは、類型の中の「療養看護型」について解説したいと思います。
一般的に、療養看護型の寄与分の判断要素は、
(ⅰ)療養看護の必要性の強さ、
(ⅱ)特別の貢献といえるか、
(ⅲ)無償又は無償類似の療養看護か、
(ⅳ)継続期間、
(ⅴ)介護に専従したか(その程度)
などを考慮して「特別の寄与」といえるかを判断していきます。
ここで、実際に寄与分が争われた東京高裁平成29年9月22日決定のケースを見ていきましょう。
【事 例】
Xは、母Aと同居をし、平成22年から、Aが亡くなる平成26年まで自宅で介護した。
Aは、認知症を発症しており、要介護度は4(介護途中から要介護5)であった。
Aは、平日の朝夕30分、土日の朝夕60分のヘルパーによる訪問介護、週1回のデイサービス、月10回程度のショートステイ、2週間に一回の看護師による訪問看護、をそれぞれ利用していたが、それ以外はXが行い、食事の介助、摘便の処置、痰の吸引などを自分で行った。
Xは、仕事をしておらず、生活費として、Aから毎月10万円を得ていた。
【家庭裁判所の判断】
参考とする介護報酬を1日あたり要介護4の期間は6670円,要介護5の期間は7500円とし、ショートステイの日数は期間から控除し、デイサービス利用日の日数は、Xによる介護は半日として計算し、さらにここから割合を0.3減じて(※おそらく職業としての介護専門職による介護ではなく親族による介護であることを考慮したものと思われます)、約655万円をXの寄与分として認定。
さらに、痰の吸引処置をXが行っていたことについて約104万円を寄与分として認め、合計で約759万円をXの寄与分として認定しました(寄与分は法定相続分にプラスされます)。
【考 察】
この事例は、療養看護型の寄与分が認められたケースとして参考になります。
上記の判断要素から考察をします。
まず、(ⅰ)療養看護の必要性の強さ、については、Aは認知症で介護度も4ないし5ということですので、強い看護の必要性が認められます。
次に(ⅱ)特別の貢献といえるか、ですが、上記の介護度のAを施設に入所させずに自宅介護したことや、摘便の処置、痰の吸引処置を行ったことは、親族間の扶養義務の範囲を超える特別の貢献といえると認定されたものと考えられます。
(ⅲ)無償又は無償類似の療養看護か、についてですが、この点は、Xは、Aからの生活費(月10万円)で生活していたということなので、無償性については若干弱い部分があろうかと考えますが、それでも貢献度の強さから、療養看護の対価を受けていたとまでは評価されなかったものと考えられます。
(ⅳ)継続期間、については約4年の期間は、相当長期ですからこれが認められています。
そして、(ⅴ)介護の専従性については、基本的にAは仕事をせずに、自宅において療養看護に努めたようですので、これが認定できます。
以上のように、寄与分の認定は、なかなかハードルの高いものですが、超高齢化社会と言われる日本社会において、高齢の親を自宅に引き取り介護を熱心に続けるというご家族も増えていると思います。
そのような場合に、介護を全くしなかった他の相続人と同じ法定相続分では、むしろ不公平だと感じる場合も少なくないものと思います。
もし、寄与分を主張できるような相続問題がありましたら、是非一度ご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
参考
民法
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。